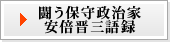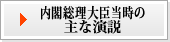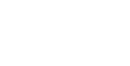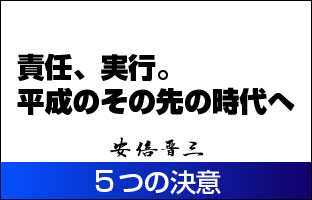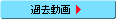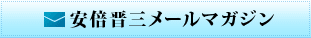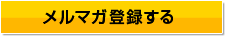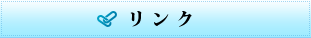トップ / 発言語録 / 著書「美しい国へ」から安倍晋三語録 / 第二章
第二章 自立する国家
- -
わたしが拉致問題を知ったとき
被害者の家族は長い間、孤独な戦いをしいられてきた。日本で声をあげれば、拉致された本人の命が保証されないと脅され、個別にツテをたどって情報を集めるしかなかったのだ。
国に見捨てられたかれらが、悲痛な思いで立ち上がっているのだ。わたしたち政治家は、それにこたえる義務がある。
わたしを拉致問題の解決にかりたてたのは、なによりも日本の主権が侵害され、日本国民の人生が奪われたという事実の重大さであった。
工作員がわが国に侵入し、わが国の国民をさらい、かれらの対南工作に使ったのである。わが国の安全保障にかかわる重大問題だ。
にもかかわらず、外務省の一部の人たちは、拉致問題を日朝国交正常化の障害としかとらえていなかった。相手のつくった土俵の上で、相手に気に入られる相撲をとってみせる――従来から変わらぬ外交手法、とりわけ対中、対北朝鮮外交の常道だった。つねに相手のペースをくずさないように協力して相撲をとれば、それなりの見返りがある。それを成果とするのが戦後の外交であった。
相手の作った土俵では戦えば勝てない
帰国後は、家族による必死の説得が行われた。その結果、五人は「北朝鮮には戻らず、日本で子どもたちの帰国を待つ」という意志を固め、中山恭子内閣官房参与とわたしに、その旨を伝えてきた。
わたしは、「かれらの意志を表に出すべきではない。国家の意志として、五人は戻さない、と表明すべきである。自由な意志決定ができる環境をつくるのは、政府の責任である」と考えていた。
マスコミや政界では、五人をいったん北朝鮮に帰すべきという意見が主流であった。しかし、ここでかれらを北朝鮮に戻してしまえば、将来ふたたび帰国できるという保証はなかった。
十月二十三、二十四日の二日間にわたって、官邸のわたしの部屋で協議をおこなった。さまざまな議論があった。
「本人の意志として発表すべきだ」、あるいは「本人の意志を飛び越えて国家の意志で帰さないといえば、本人の意志を無視するのはおかしい、とマスコミに批判されるだろう。家族が離ればなれになれば、責任問題にもなる」という強い反対もあった。
しかしわたしたちは、彼らは子どもたちを北朝鮮に残しているのだから、彼らの決意を外に出すべきではない、と考えた。
何より被害者が北朝鮮という国と対峙しようとしているとき、彼らの祖国である日本の政府が、国家としての責任を回避することは許されない。
最終的にわたしの判断で、「国家の意志として五人は帰さない」という方針を決めた。ただちに小泉総理の了承を得て、それは政府の決定となった。
日朝平壌宣言にしたがって開かれる日朝国交正常化交渉の日程は、10月29日と決まっていた。政府が「五人を帰さない」という方針を北朝鮮に通告したのは、その五日前のことであった。
その日、ある新聞記者に「安倍さん、はじめて日本が外交の主導権を握りましたね」といわれたのを鮮明に覚えている。たしかにそのとおりだった。
「知と情」論で政府を攻撃したマスコミ
「五人を北朝鮮に戻さない」という政府の決定を、あのときマスコミは、かならずしも支持しなかった。「政府が家族を引き離した」と、こき下ろす新聞もあった。
当時、ある新聞がさかんに書き立てたのが、「知と情」という言葉である。「拉致被害者はかわいそうだから助けてあげたいが、それは情の問題だ。これに対して北朝鮮の核は安全保障上の重大事であって知の問題だ。ここは冷静になって知を優先すべきだ」というのである。
わたしは徹底的に反論した。
「拉致の責任を追及するのは、たんに情にかられてのことではない。大韓航空機爆破事件の犯人、金賢姫が田口八重子さんから日本人化教育を受けたことからもわかるように、拉致は北朝鮮の国際テロの一環として行われたものであって、それはまさしく安全保障上の問題なのである。それを三面記事的な情の問題におとしめるのは意図的な情報操作としか思えない」
マスコミは拉致問題の解明に消極的だった。社説で「拉致は犯罪である」と書きはするが、それは「いちおう拉致問題を批判した」というアリバイのようなものであった。ほんらい別個に考えるべき、かつての日本の朝鮮半島支配の歴史をもちだして、正面からの批判を避けようとするのである。自民党のなかにも、「知と情」論をふりかざす議員がいた。
自由を担保するのは国家
このソ連の日本侵攻について、ロンドン大学教授の森嶋通夫氏と早大客員教授の関嘉彦氏との間でたたかわされた有名な防衛論争がある。「北海道新聞」と「文藝春秋」誌上で展開された議論だが、森嶋氏は、核兵器の時代に通常兵器で武装しても無意味で、どうせ降参するなら武装はゼロでよい、としたうえで、「不幸にして最悪の事態が起れば、白旗と赤旗をもって、平静にソ連軍を迎えるより他ない。三十四年前に米軍を迎えたようにである。そしてソ連の支配下でも、私たちさえしっかりしていれば、日本に適合した社会主義経済を建設することは可能である。アメリカに従属した戦後が、あの時徹底抗戦していたよりずっと幸福であったように、ソ連に従属した新生活も、また核戦争をするよりもずっとよいにきまっている」と述べた。
個人の自由と国家との関係は、自由主義国家においても、ときには緊張関係ともなりうる。しかし、個人の自由を担保しているのは国家なのである。それらの機能が他国の支配によって停止させられれば、天賦の権利が制限されてしまうのは自明であろう。
この論争がたたかわされてから四半世紀、わたしたちはすでに、ソビエト連邦がどのように消滅し、冷戦がどのように終焉したかを知っている。
「靖国批判」はいつからはじまったか
国家を語るとき、よく出てくるのが靖国参拝問題であり、「A級戦犯」についての議論である。戦後60年をむかえた2005年は、とくにはげしかった。
靖国問題というと、いまでは中国との外交問題であるかのように思われているが、これはそもそもが国内における政教分離の問題であった。いわゆる「津地鎮祭訴訟」の最高裁判決(1977年)で「社会の慣習にしたがった儀礼が目的ならば宗教的活動とみなさない」という合憲の判断が下されて以来、参拝自体は合憲と解釈されているといってよい。首相の靖国参拝をめぐって過去にいくつかの国賠訴訟が提起されているが、いずれも原告敗訴で終わっている。
政府としては、85年に藤波孝生官房長官の国会答弁で「戦没者の追悼を目的として、本殿または社頭で一礼する方式で参拝することは、憲法の規定に違反する疑いはない」という見解を示して以来、参拝は合憲という立場をくずしていない。
中国とのあいだで靖国が外国問題化したのは、85年8月15日、中曾根首相の公式参拝がきっかけである。
中曾根参拝の一週間前の8月7日、朝日新聞が次のような記事を載せた。
「(靖国参拝問題を)中国は厳しい視線で凝視している」
日本の世論がどちらの方を向いているかについて、つねに関心をはらっている中国政府が、この報道に反応しないわけがなかった。参拝前日の8月14日、中国外務省のスポークスマンは、はじめて公式に、首相の靖国神社の参拝に反対の意思を表明した。「(首相の靖国参拝は)アジア各国の人民の感情を傷つける」というわけである。「A級戦犯が合祀されているから」という話がでたのは、このときだ。
「A級戦犯」といういい方自体、正確ではないが、じつは、かれらの御霊が靖国神社に合祀されたのは、それより7年も前の1978年、福田内閣のときなのである。その後、大平正芳、鈴木善幸、中曾根康弘と、三代にわたって総理大臣が参拝しているのに、中国はクレームをつけることはなかった。
1978年に結ばれた日中平和友好条約の一条と三条では、たがいに内政干渉はしない、とうたっている。一国の指導者が、その国のために殉じた人びとにたいして、尊崇の念を表するのは、どこの国でもおこなう行為である。また、その国の伝統や文化にのっとった祈り方があるのも、ごく自然なことであろう。
2005年6月、わたしは、訪日中のインドネシアのユドヨノ大統領にお会いしたとき、小泉総理の靖国参拝について、「わが国のために戦い、命を落とした人たちにたいして、尊崇の念をあらわすとともに、その冥福を祈り、恒久平和を願うためです」と説明した。すると大統領は、「国のために戦った兵士のためにお参りするのは当然のことです」と理解を示してくれた。世界の多くの国々が共感できることだからではないだろうか。
「A級戦犯」をめぐる誤解
「A級戦犯」についても誤解がある。「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判=東京裁判で、「平和に対する罪」や「人道に対する罪」という、戦争の終わったあとにつくられた概念によって裁かれた人たちのことだ。国際法上、事後法によって裁いた裁判は無効だ、とする議論があるが、それはべつにして、指導的立場にいたからA級、と便宜的に呼んだだけのことで、罪の軽重とは関係がない。
「A級戦犯」として起訴された28人のうち、松岡洋右らふたりが判決前に死亡し、大川周明が免訴になったので、判決を受けたのは25人である。このうち死刑判決を受けて刑死したのが東条英機ら7人で、ほか5人が受刑中に亡くなっている。
ところが同じ「A級戦犯」の判決を受けても、のちに赦免されて、国会議員になった人たちもいる。賀屋興宣さんや重光葵さんがそうだ。賀屋さんはのちに法務大臣、重光さんは、日本が国連に加盟したときの外務大臣で、勲一等を叙勲されている。
日本はサンフランシスコ講和条約で極東国際軍事裁判を受諾しているのだから、首相が「A級戦犯」の祀られた靖国神社へ参拝するのは、条約違反だ、という批判がある。ではなぜ、国連の場で、重光外相は糾弾されなかったのか。なぜ、日本政府は勲一等を剥奪しなかったのか。
それは国内法で、かれらを犯罪者とは扱わない、と国民の総意で決めたからである。1951年(昭和26年)、当時の法務総裁(法務大臣)は、「国内法の適用において、これを犯罪者とあつかうことは、いかなる意味でも適当ではない」と答弁している。また、講和条約が発効した52年には、各国の了解も得たうえで、戦犯の赦免の国会決議もおこなっているのである。「B・C級戦犯」といわれる方たちも同様である。ふつう禁固3年より重い刑に処せられた人の恩給は停止されるが、戦犯は国内法でいう犯罪者ではないので、恩給権は消滅していない。また、戦傷病者戦没者遺族等援護法にもとづいて遺族年金も支払われている。